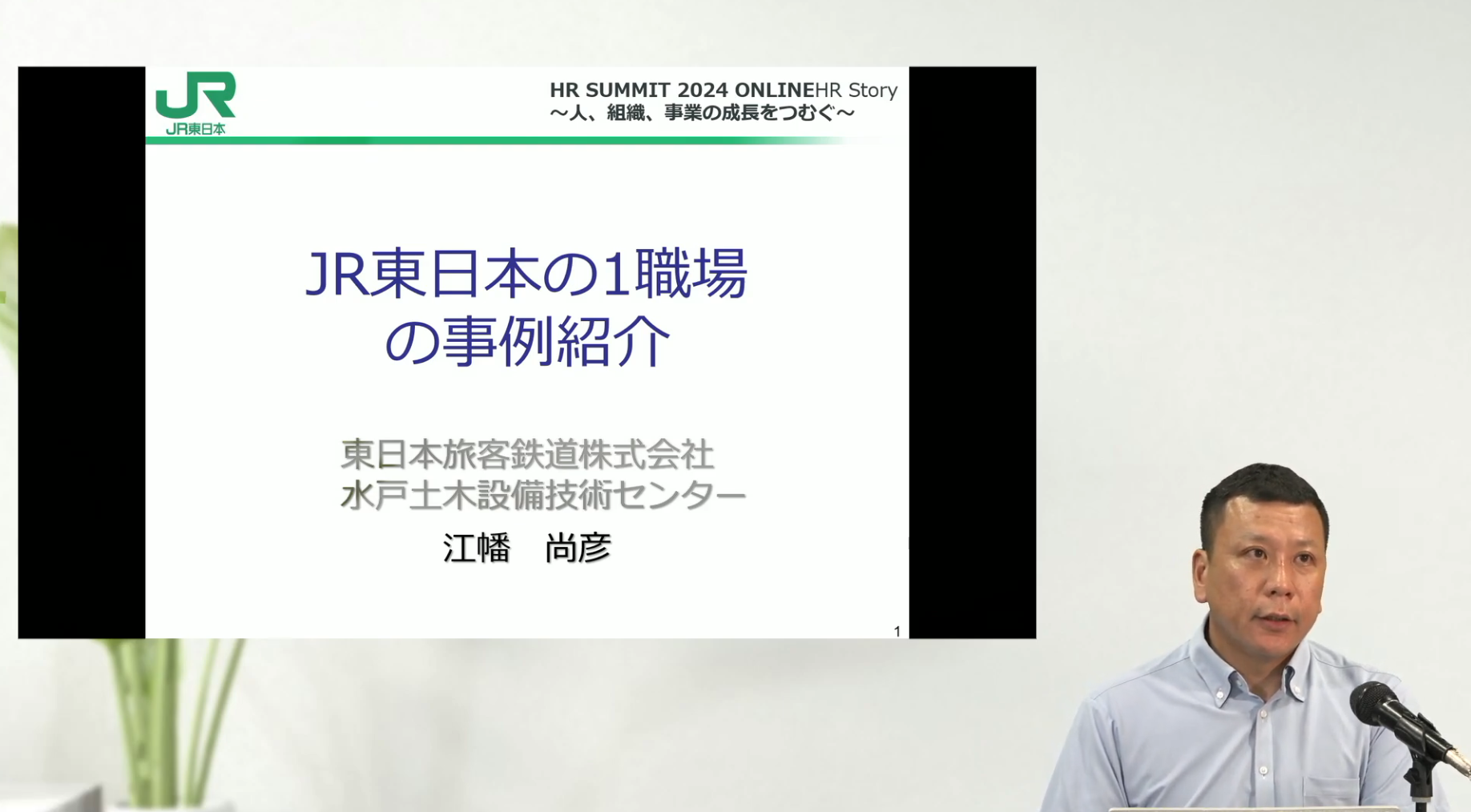
東日本旅客鉄道株式会社 様
個人に「応じて、適切な」動機づけを行う人材育成にAttunedを活用

AI × モチベーションで、"モチベーション"を可視化。モチベーションアセスメントやAI TalkCoachを活用し、チームのパフォーマンスとエンゲージメントを向上させましょう!
ダウンロードはこちら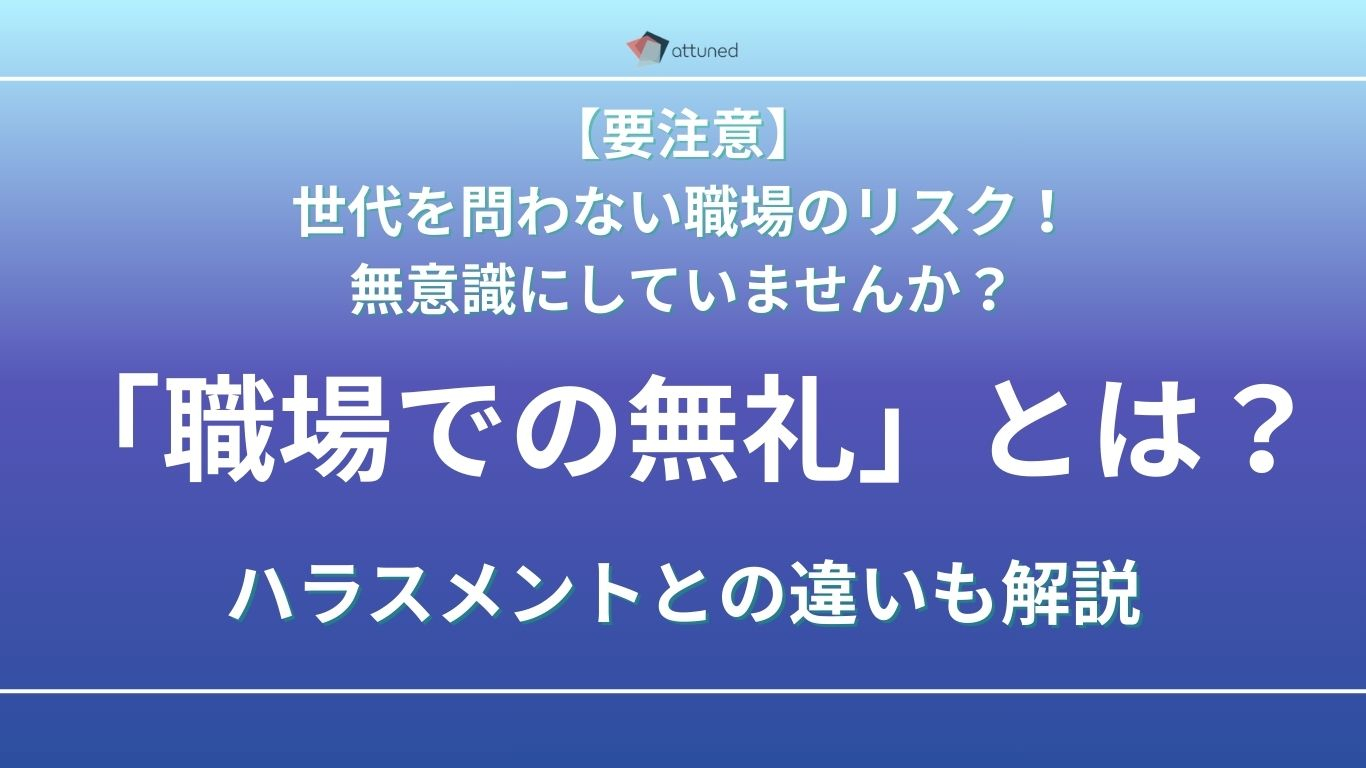
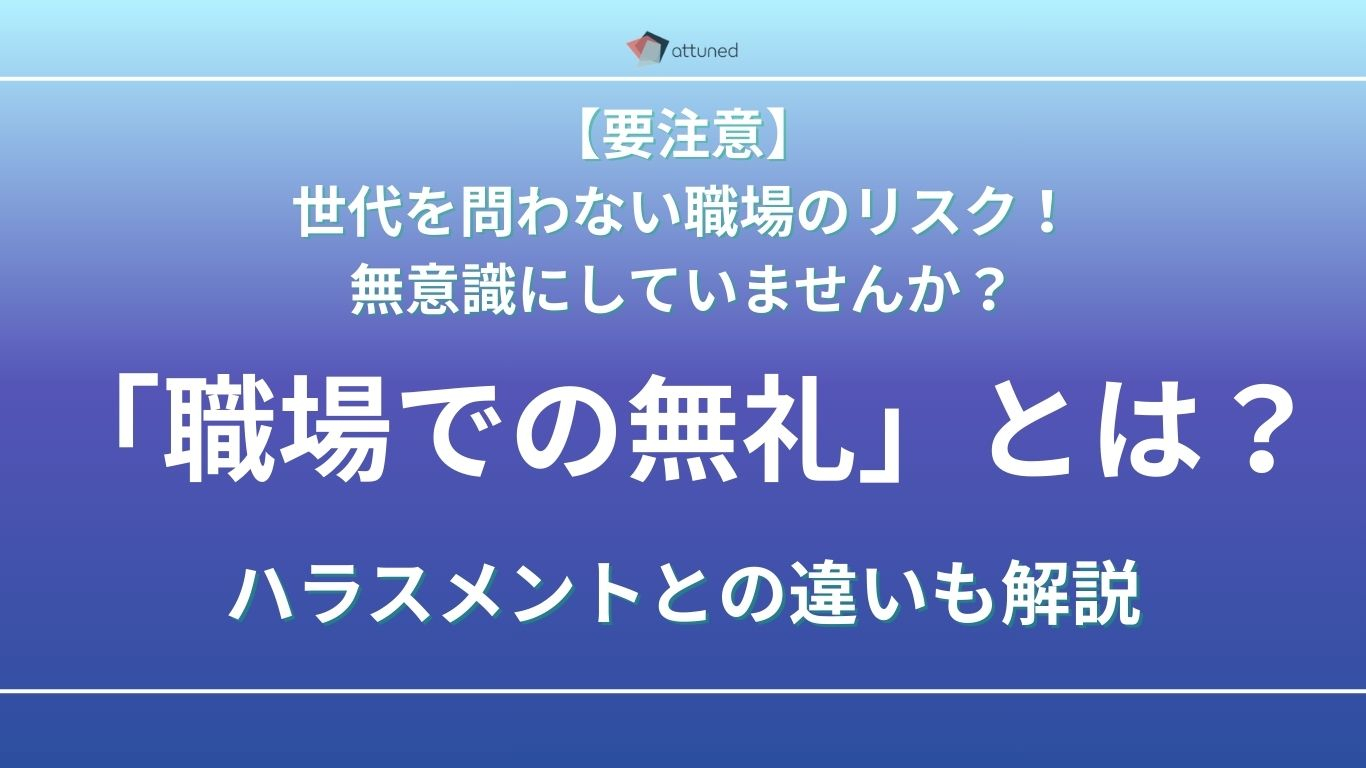
米国の研究では、職場における「インシビリティ行為(無礼)」が年間で 270億ドル規模の経済的損失 を生んでいると報告されています。
無礼とは、強い意図を持ったハラスメントではなく、曖昧で低強度な逸脱行為を指します。
たとえば、人の発言をさえぎる、当人のいないところで否定的な話をする、会議中にスマートフォンをいじる...
こうした小さな行為が、組織の健全性を損ねるのです。
本記事では、無礼の定義やハラスメントとの違い、アメリカで注目が高まる背景、日本企業への示唆について整理します。
目次1 職場でのインシビリティ行為(Workplace Incivility)の定義2 アメリカで注目が高まった背景 3 ハラスメントとの違い 4 日本企業における課題と示唆 5 企業が取り組むべき対応 6 おわりに |
学術研究では、は次のように定義されています。
「対象者を傷つける意図が曖昧で、職場における尊重の規範に反する低強度の逸脱行為」
つまり「悪意があるのかないのか判別しにくいが、受け手に不快感を与える行為」です。
例として:
挨拶を無視する
人の話を遮る
軽んじる発言をする
打ち合わせ中に別作業をする
これらは一過性の「何気ない行為」であっても、繰り返されれば組織全体に深刻な影響を及ぼします。


2024年の米国大統領選挙をはじめ、職場に政治的な話題が持ち込まれる機会が増えています。
近年は職場において、かつてとは異なり政治の話はタブーではなくなりつつあるがものの、やはりセンシティブであることは確かで、一歩間違えば「インシビリティ行為(無礼)」へ発展します。
世界的な地政学リスクも相まって、「インシビリティ行為(無礼)」のリスクは高まっているのです。
従来はHR領域で扱われてきた「インシビリティ行為(無礼)」が、近年は ビジネス倫理や経営学のテーマ としても論じられています。
たとえば「女性は男性より沈黙を選びやすい」といった性差の研究も進み、インクルージョンやDEIとの関連が注目されています。
コロナ禍でリモートワークが広がった時期には、物理的距離が無礼の発生機会を抑えていました。しかし出社回帰が進む現在、対面コミュニケーションの場が増え、再び「インシビリティ行為(無礼)」が目立つようになっています。
「インシビリティ行為(無礼)」とハラスメントは混同されがちですが、次の点で区別されます。
意図
ハラスメント:対象者を意図的に傷つける行為
「インシビリティ行為(無礼)」:意図が曖昧で、不快感を与えるが明確な攻撃ではない
継続性
ハラスメント:繰り返され、標的が明確
「インシビリティ行為(無礼)」:一過性の行為も含まれる
法的対応
ハラスメント:法的に問題となり得る
「インシビリティ行為(無礼)」:一般的に法的対応の対象外
「インシビリティ行為(無礼)」は「標準的な行為」と「ハラスメント」の間にある グレーゾーン と言えます。
国や文化によってその解釈は異なり、企業の対応方針が分かれるところです。
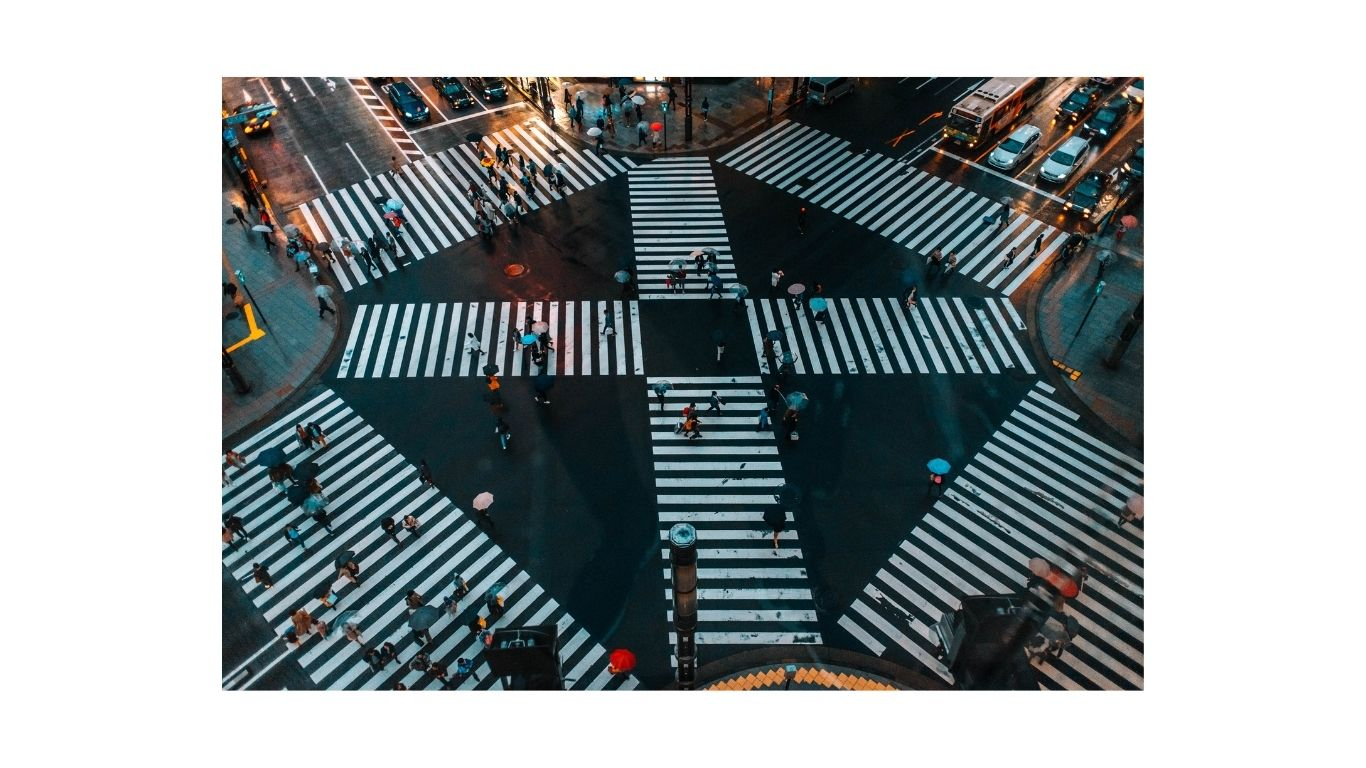
日本ではセクハラやパワハラといった「ハラスメント」への認知は高い一方で、「インシビリティ行為(無礼)」はすぐに「ハラスメント」と一括りにされがちです。その結果、管理職が萎縮し、適切な指導まで避けてしまうケースも見られます。
従業員自身が「これは『インシビリティ行為(無礼)』なのか、ハラスメントなのか」を判断できないことも多いのが現実です。そのため、曖昧なまま放置されるか、逆に過剰に問題視されてしまいます。
今こそ日本企業に求められるのは、「『インシビリティ行為(無礼)とは何か」「どのような行為が対象となるか」 を明文化し、社員に浸透させることです。ハラスメントポリシーは整備されつつありますが、「インシビリティ行為(無礼)」へのガイドラインを持つ企業はまだ少数派です。
「インシビリティ行為(無礼)」の定義を共有する
ハラスメントと区別したうえで、自社の文化に照らして「望ましくない行為」を明示する。
教育・研修の導入
日常のコミュニケーションに潜む無礼をケーススタディで学び、気づきを促す。
現場の声を吸い上げる仕組み
サーベイや1on1で「人間関係の困りごと」を可視化する。
リーダーの模範行動
上司が率先して挨拶や感謝を実践し、部下の意見を遮らずに聞くことで、文化が変わる。

「インシビリティ行為(無礼)」はハラスメントほど深刻に見えないため、軽視されがちです。しかし実際には、離職率の上昇や生産性低下といった 経営リスク に直結します。
日本企業にとって重要なのは、「『インシビリティ行為(無礼)』をゼロにする」ことではなく、「無礼が生じたときにどう扱うか」を全員が理解している状態 をつくることです。
ハラスメント対策の次の課題として、今こそ「インシビリティ行為(無礼)」に光を当てるべき時が来ています。
Attunedは、心理学に基づいた個人モチベーションの可視化をベースとしたエンゲージメントサービスです。やりがい創出、生産性向上、離職防止、心理的安全性の向上、人材育成・マネージャー育成などに効果的なソリューションを提案しています。
さらに詳しくサービスの内容をご覧になりたい方はこちらから資料をダウンロードしてください。
Attunedでは2週間の無料トライアルを実施しています。ご興味のある方はこちらからチェックしてください!
こちらの記事も、あわせて読まれています

人の自分の価値観が異なることを客観的に理解することがいかに大切か、Attunedを通して体験してみませんか?
Read More



組織にも「レジリエンス」の価値が問われるようになりました。今回は、個々の視点から組織レジリエンス(「厳しい状況や変化に対応し、成長する力」)について考え、その具体的な実現方法について探ってみましょう。
Read More


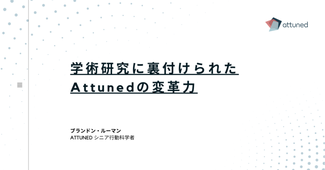
Attunedは企業が社員の内発的動機を理解し、活用するための支援を行っています。そこで得られたインサイトによって、企業はモチベーションのギャップや盲点を特定し、社員にとってより意味ある仕事、そしてより仕事に積極的になれる職場環境の構築に活用することが出来ます。
Read More


ブログ一覧を見る




お役立ち資料
2025年のモチベーションランキングレポートが完成しました。このレポートは、世界中のAttunedユーザーの皆様のモチベーションの変化を、学術界や産業界のエキスパートの視点を取り入れ、詳細に分析した非常に貴重なデータに基づいています。
社員のエンゲージメントを高める、心理的安全性の高い職場とは何かが理解できるホワイトペーパーです。「心理的安全性」と「内発的動機づけ」について詳しく解説します。
一覧を見る

『Attuned』の導入に関してご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

各種資料やオリジナルサマリーを
【無料】でダウンロードできます

まずは無料でお試ししませんか?
ご利用方法もサポートいたします

見積りを依頼したい、導入の流れを
知りたいなど何でもご相談ください
