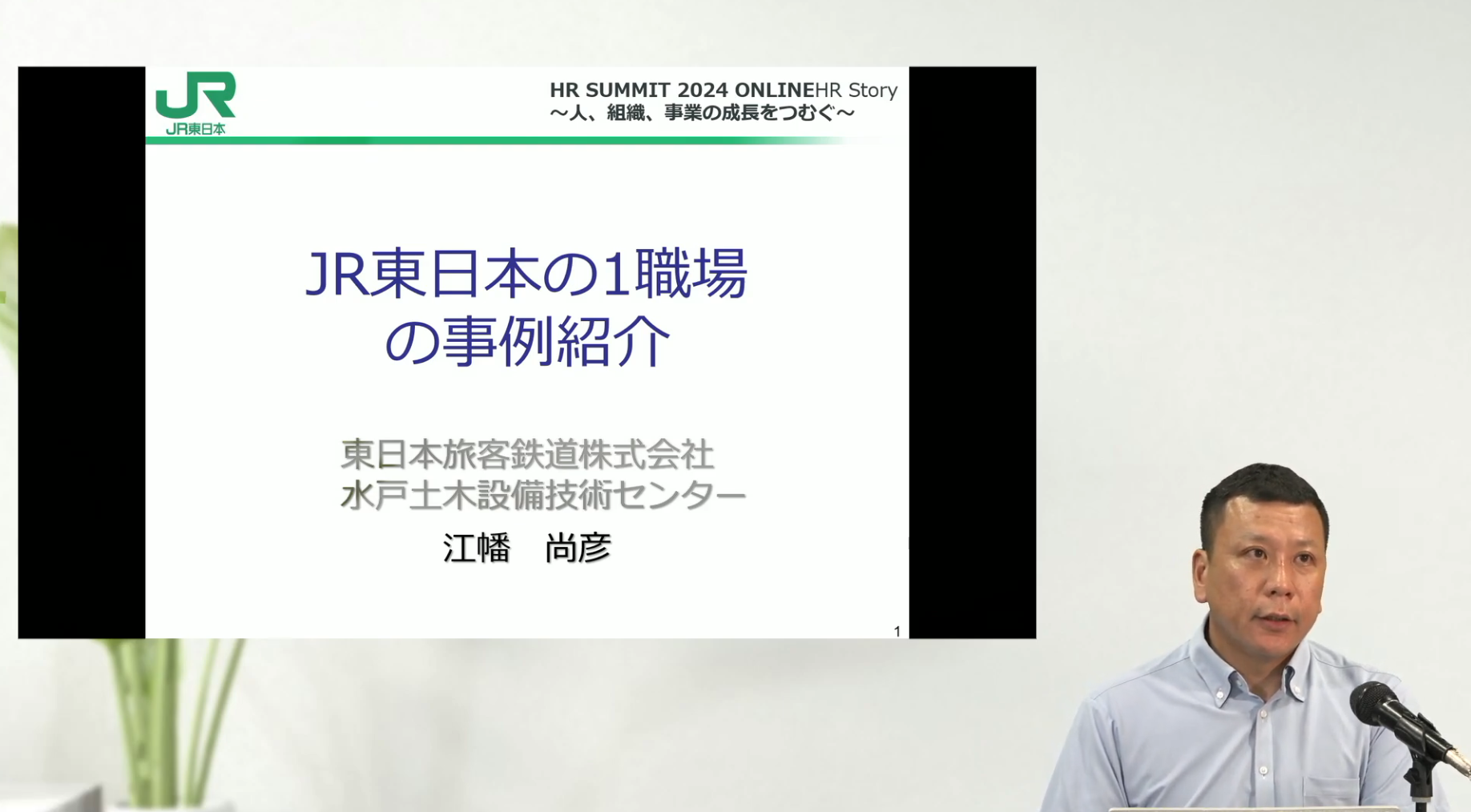
東日本旅客鉄道株式会社 様
個人に「応じて、適切な」動機づけを行う人材育成にAttunedを活用

AI × モチベーションで、"モチベーション"を可視化。モチベーションアセスメントやAI TalkCoachを活用し、チームのパフォーマンスとエンゲージメントを向上させましょう!
ダウンロードはこちら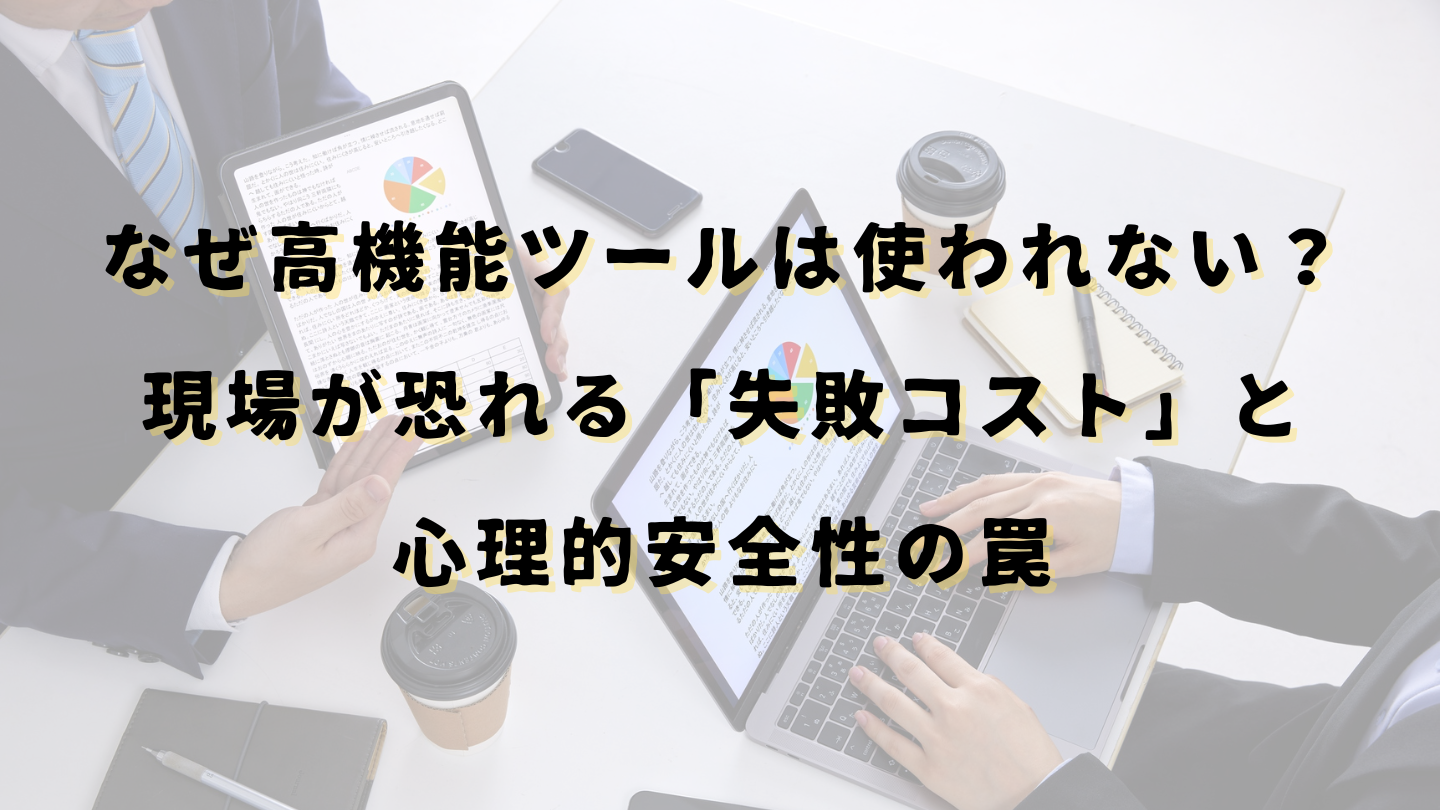
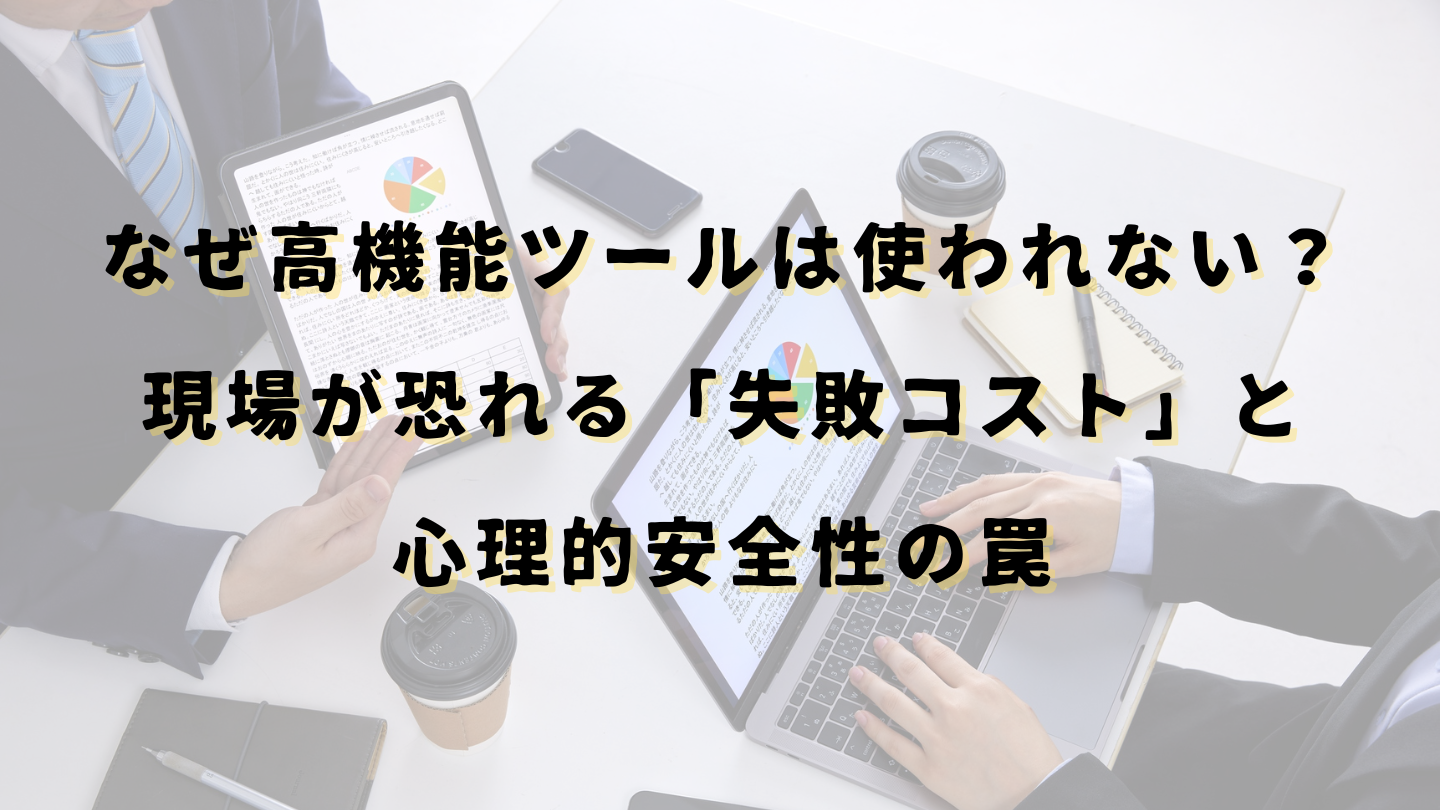
「研修もした。マニュアルも完璧だ。なのに、なぜ現場はあの高機能ツールを使わないんだ!」
DXを推進するマネージャーとして、そう頭を抱えたことはありませんか?
もしその原因を「現場の抵抗が強いから」と結論づけているなら、危険信号です! 彼らが本当に恐れているのは、私たちが思う「学習コスト」ではなく、回復不能な「失敗コスト」の恐怖。それは怠慢ではなく、合理的な"自己防衛"かもしれません!
目次 |
DXを推進する際、私たちは「新しいツールの使い方を覚える時間=学習コスト」にばかり注目しがちです。研修時間を確保し、手厚いマニュアルを整備すれば、いずれ使われるようになるだろう、と。
しかし、現場が直面しているプレッシャーは、それほど単純ではありません。 特に、業務の根幹に関わる「高機能」なツールは、必然的に「操作ミス」のリスクを伴います。
「もし、このボタンを押し間違えたら、顧客データを上書きしてしまうかもしれない」 「万が一、間違った相手に請求書を送ってしまったら?」 「基幹データを壊したら、回復にどれだけの工数がかかるか...いや、回復不可能な失敗になったらどうしよう」
これらは単なるミスでは済まされない、重大なインシデントにつながる恐怖です。これが「失敗コスト」です。
この恐怖は、ツールの機能が高度であればあるほど、そしてそのツールが扱うデータが重要であればあるほど増大していきます。現場は「便利になるかもしれない」という期待よりも、「取り返しのつかない失敗をするかもしれない」という恐怖を、日々感じているのです。
この「失敗コスト」への恐怖が、DXの強力なブレーキとなる背景には、組織の「心理的安全性」が深く関わっています。
もし、あなたの組織が「失敗は許されない」「ミスをしたら厳しく追及される」「誰がやったんだと犯人探しが始まる」...そんな文化だったら、従業員はどう行動するでしょうか。
彼らは、この「失敗コスト」を極度に恐れます。 新しいツールは、彼らにとって「業務を効率化する便利な道具」である以前に、「自らのキャリアを脅かす爆弾」のように見えてしまうのです。
マネージャーが「なぜ使わないんだ」と進捗を管理しようとすればするほど、現場は「失敗」を隠そうとします。そして、失敗を隠す最も簡単な方法は、「挑戦しないこと」=「ツールを使わないこと」になってしまいます。

さらに問題を深刻にするのが、推進体制の「丸投げ」です。 十分なサポート体制がなかったり、「こんなことも分からないのか」という雰囲気があったりすると、従業員は「操作が分からない」と声を上げること自体をためらいます。
これは「無知を晒す恐怖」です。 「こんな初歩的な質問をしたら、DXについていけない人材だと思われるのではないか」 「今さら『分からない』と言えば、低評価につながるのではないか」
そうした不安が、彼らを「分からないまま放置する」という選択に追い込みます。
この環境下で、従業員が取る最も合理的で、唯一安全な行動は何でしょうか。 それは「リスク(=失敗コスト)をゼロにすること」。すなわち、「新しいツールに触らない(=使わない)」ことです。
では、どうすれば現場はこの恐怖を乗り越え、新しいツールを前向きに使いこなそうとしてくれるのでしょうか。
答えは、心理的安全性が高い組織(失敗が学習と見なされる組織)を作ることです! 「間違えるかもしれないが、まずは試してみよう」 「分からなければ、すぐに聞こう」 こうした前向きな行動が許容され、むしろ推奨される環境です。
具体的には、推進部門が「失敗しても良い練習環境(サンドボックス)」を徹底的に用意すること。あるいは、「どんな初歩的な質問でも歓迎する」「質問してくれてありがとう」というサポート体制を明確に打ち出し、それをマネージャー自らが実践することです。
失敗コストへの恐怖をゼロにすることはできません。しかし、失敗を「個人の責任」として追及するのではなく、「チームの学習機会」として捉え直す文化があれば、現場は安心してその恐怖を乗り越え、学習を進めることができます。

マネージャーの皆さん、もしチームが新しいツールを使おうとしないなら、それは決して彼らの怠慢や変革への抵抗ではありません。
それは、失敗が許容されず、サポート体制も不十分な(=心理的安全性が欠如した)環境で、自らの職務と評価を守るために取った、最も合理的な「自己防衛」の結果なのです。
この「失敗コストへの恐怖」という心理的負荷を軽減する安全装置なしに、高機能なツールだけを導入するDXは、現場の恐怖心を最大化させ、必然的に「使われない」という敗戦を迎えてしまいます。
DXを本当に成功させたいのであれば、導入するツールの機能比較に時間を費やす前に、まず自組織の「安全装置」が正しく機能しているかを確認すべきではないでしょうか。従業員が安心して「失敗」できる土壌、すなわち心理的安全性を確保することこそが、成功への第一歩です!
Attunedは、心理学に基づいた個人モチベーションの可視化をベースとしたエンゲージメントサービスです。やりがい創出、生産性向上、離職防止、心理的安全性の向上、人材育成・マネージャー育成などに効果的なソリューションを提案しています。
さらに詳しくサービスの内容や料金体系をご覧になりたい方はこちらから資料をダウンロードしてください。
Attunedでは2週間の無料トライアルを実施しています。ご興味のある方はこちらからチェックしてください!
こちらの記事も、あわせて読まれています
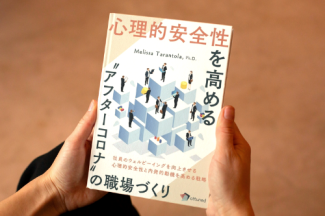
Attunedの心理学者であるメリッサ・タラントラ博士による、最新のホワイトペーパー「心理的安全性を高める"アフターコロナ"の職場づくり」を公開いたしました。
Read More



Attunedの心理学者であるメリッサ・タラントラ博士による、 最新のホワイトペーパー「心理的安全性を高める"アフターコロナ"の職場づくり」を公開いたしました。
Read More



2021年9月15日(水)、HRサミット2021 ONLINE【ライブ配信講演】にて、Attunedは「自律型人材と支援型リーダー育成の鍵は 「内発的動機の見える化」〜マネージャーの「対話力」強化とジョブ・クラフティングのポイント」と題したセミナーを行いました。
Read More


ブログ一覧を見る




『Attuned』の導入に関してご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

各種資料やオリジナルサマリーを
【無料】でダウンロードできます

まずは無料でお試ししませんか?
ご利用方法もサポートいたします

見積りを依頼したい、導入の流れを
知りたいなど何でもご相談ください
